ここで浅井は、『三大秘法抄』の「勅宣・御教書」を勝手に解釈して「国立戒壇」の根拠としていますが、日蓮正宗でそのような解釈をすることはありません。また浅井は、富士大石寺門流で「国立戒壇」と呼称してきたなどと嘯(うそぶ)いていますが、明治以前の日蓮正宗の歴史にそのような事実はありません。
古来、宗門において『三大秘法抄』は宗旨の根幹に関わる重要御書として、安易に解釈することは許されませんでした。そのため『三大秘法抄』の解釈書は、きわめて数少ないものでした。
近年に至って日淳上人が『三大秘法抄』を講義されましたが、その一文に、
勅宣は国主の「みことのり」で御教書とは当時将軍の令書であります。此(こ)れは国政の衝(しょう)に当(あた)る人より出る教詞(きょうし)と解すべきであります(淳全 四八八)
と仰せられています。しかし「勅宣・御教書」をもって「国立戒壇」の根拠としてはいけないのです。
このことからも、浅井の言い分は、慢心(まんしん)による妄言(もうげん)という他はありません。
古来、宗門において『三大秘法抄』は宗旨の根幹に関わる重要御書として、安易に解釈することは許されませんでした。そのため『三大秘法抄』の解釈書は、きわめて数少ないものでした。
近年に至って日淳上人が『三大秘法抄』を講義されましたが、その一文に、
勅宣は国主の「みことのり」で御教書とは当時将軍の令書であります。此(こ)れは国政の衝(しょう)に当(あた)る人より出る教詞(きょうし)と解すべきであります(淳全 四八八)
と仰せられています。しかし「勅宣・御教書」をもって「国立戒壇」の根拠としてはいけないのです。
このことからも、浅井の言い分は、慢心(まんしん)による妄言(もうげん)という他はありません。

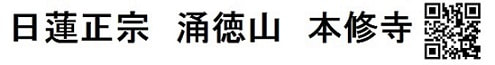
 RSSフィード
RSSフィード
