33.阿部日顕(上人)は「三大秘法抄」を次のごとくねじ曲げた。
「王法」を「政治をふくむあらゆる社会生活の原理」と歪曲(わいきょく)し、
「王臣」を「民衆」とたばかり、
「有徳王」を「池田先生」と諮(へつら)い、
「勅宣並びに御教書」を「建築許可証」と偽り、
「霊山浄土に似たらん最勝の地」を「大石寺境内(けいだい)」とごまかし、
「時を待つべきのみ」を「前以(もっ)て建ててよい」などとねじ曲げた。
(顕正新聞 平成三三年四月五日号二面趣意、基礎教学書 一三八四·四四六趣意)
これは主に、日顕上人が教学部長時代に執筆された『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』という著述の内容についての誹謗(ひぼう)ですが、全く見当達いの暴言です、
正本堂建立当時は、創価学会を中心に、八百万という広宣流布進展の成果があり、広宣流布も間近であるという機運が宗門に高まっていました。そうしたなかで、本門戒壊の大御本尊の御威徳(いとく)を、広く世界に知らしめるべき大殿堂を建立するということとなり、当時の状況を『三大秘法抄』『一期弘法付属書』の御文を擬(なぞら)えて、 「国立戒壇論の誤りについて』や「本門事の戒壇の本義』において、試みの解釈がなされたのです。
しかし、それは日達上人の「訓諭」における「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」 (設問42参照)という御指南の御意を拝して解釈されたものであり、日顕上人が勝手に「ねじ曲げた」などというものではありません。
① 「王法」について
第六十五世日淳上人は、
王法仏法に冥(みょう)じ、仏法王法に合してと仰せ玉ふは王法とは国王が政治を行ふその拠(よ)りどころである法であります。また一般世間の法にも通ふところで、仏法の出世間(しゅっせけん)法なるに対し
世間法を意味せられるのであります(淳全 四八七)
と、広く世間法を含むことを教示されています。したがって、現在においては王法を、政治をふくむあらゆる社会生活の原理(国立戒壇論の誤りについて三九)と解釈するのは至極(しごく)当然です。
②「王臣」について
顕正会はあくまで日本の王は天皇であり、天皇の勅宣(ちょくせん)が広宣流布の必須条件であると主張しています。
しかし、現在の天皇は日本の象徴であり、一国の主権者は国民一人一人です。
この意味からして、
現代では、民衆が王であるとともに臣である(同五一)
と言われたのは当然のことです。
③ 「有徳王」について
これは教学部長時代の日顕上人が昭和四十一年の第二十九回学会本部総会の祝辞(大日蓮昭和四一年六月号一五)において、有徳王·覚徳比丘(びく)の例を挙げて、僧俗のあるべき姿を称賛する意味で引用されたものであって、『三大秘法抄』の意義を正式に解釈されたものではありません。池田大作に対して、日達上人および宗門をさらに外護(げご)するよう激励されたのです。
④「勅宣·御教書」について
勅宣や御教書は、為政者(いせいしゃ)が命令をしたり認可を与える際に発布(はっぷ)する令書です。『三大秘法抄』の「勅宣·御教書」にも、建設に対する為政者の許認可という意味合いが含まれています。
したがって、「勅宣·御教書」を、あえて「建築許可証」と解釈されたのです。
しかし、後に日顕上人は、
「勅宣·御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。
(近現代における戒壇問題の経緯と真義九八)
と仰せられています。
⑤ 「時を待つべきのみ」を「前以て建ててよい」などとねじ曲げた
昭和四十七年四月二十八日、日達上人は宗内全般に対して、
正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即(すなわ)ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。但(ただ)し、現時にあっては未(いま)だ
誇法の徒(と)多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇(しゅみだん)は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり
(達全二ー一三、昭和四七年六月号二)と「訓論」を発令されました。
これについて、当時の阿部教学部長(日顕上人)の『国立戒壇論の誤りについて』に、
従って正本堂は現在直ちに一期弘法抄、三大秘法抄に仰せの戒壇ではないが、将来その条件が整ったとき、本門寺の戒壇となる建物で、それを今建てるのであると、日達上人が明鑑(めいかん)あそばされ、示されたのが此の度の訓諭であろう(該書 六四)
と解釈しました。
これは、正本堂建立時は誇法の徒が多く、広宣流布の達成ではないものの、いよいよ折伏弘通に励み、近く広宣流布を達成して、名実ともに正本堂を御遺命の戒壇にするという、宗門僧俗の願望を、正本堂に込められたものです。
⑥ 「霊山浄土に似たらん最勝の地」を「大石寺境内」とごまかしている
大石寺が本門戒壇建立の地であることについては、日興上人の『富士一跡門徒存知事』に、
「駿河国(するがのくに)富士山は広博(こうぱく)の地なり。一には扶桑(ふそう)国なり、二には四神相応(しじんそうおう)の勝地なり」
(御書 一八七三)
とあり、本門戒壇は四神相応の地に建立すべきことを御教示されています。
第五十九世日亨上人は、四神相応を検討されて、
ここの地は、河合(かわい)よりやや朗開(ろうかい)せるも、半里をへだつる大石が原の景勝にしかず。ただちに富嶽(ふがく)を負い駿湾(すんわん)をのぞみ、一望千里臓宏(こうこう)たる高原にして、なお原始の処女林にあり。加うるに大道あり河沢(かたく)あり、四神相応の霊地なり(詳伝 二四一 )
と、大石寺が四神相応の霊地であると判じられ、大石寺こそが本門戒壇建立の地であることを御教示されています。
また、顕正会の前身である妙信講機関誌の『冨士』にも、
下条より約半里ほど離れた北方に大石ヵ原という若々(ぼうぼう)たる平原がある。後には富士を背負い、前には洋々たる駿河湾をのぞみ、誠に絶景の地であり、日興上人はこの地こそ、本門戒壇建立の地としての最適地と決められ、ここに一宇(う)の道場を建立されたのである。かくて、日興上人は弘安二年の戒壇の大御本尊をここに厳護されると共に、広宣流布の根本道場として地名に因(ちな)んで多宝富士大日蓮華山大石寺と号されたのである。これが日蓮正宗富士大石寺の始(はじま)りである
(富士 昭和三九年九月号二三)
との記述があります。
過去には妙信講も、大石寺こそ本門戒壇建立の地であると断じていたのであり、浅井の「霊山浄土に似たらん最勝の地を大石寺境内とごまかし」
という誹謗(ひぼう)は、自分たちの過去の言葉に言いがかりを付けているに過ぎません。
「王法」を「政治をふくむあらゆる社会生活の原理」と歪曲(わいきょく)し、
「王臣」を「民衆」とたばかり、
「有徳王」を「池田先生」と諮(へつら)い、
「勅宣並びに御教書」を「建築許可証」と偽り、
「霊山浄土に似たらん最勝の地」を「大石寺境内(けいだい)」とごまかし、
「時を待つべきのみ」を「前以(もっ)て建ててよい」などとねじ曲げた。
(顕正新聞 平成三三年四月五日号二面趣意、基礎教学書 一三八四·四四六趣意)
これは主に、日顕上人が教学部長時代に執筆された『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』という著述の内容についての誹謗(ひぼう)ですが、全く見当達いの暴言です、
正本堂建立当時は、創価学会を中心に、八百万という広宣流布進展の成果があり、広宣流布も間近であるという機運が宗門に高まっていました。そうしたなかで、本門戒壊の大御本尊の御威徳(いとく)を、広く世界に知らしめるべき大殿堂を建立するということとなり、当時の状況を『三大秘法抄』『一期弘法付属書』の御文を擬(なぞら)えて、 「国立戒壇論の誤りについて』や「本門事の戒壇の本義』において、試みの解釈がなされたのです。
しかし、それは日達上人の「訓諭」における「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」 (設問42参照)という御指南の御意を拝して解釈されたものであり、日顕上人が勝手に「ねじ曲げた」などというものではありません。
① 「王法」について
第六十五世日淳上人は、
王法仏法に冥(みょう)じ、仏法王法に合してと仰せ玉ふは王法とは国王が政治を行ふその拠(よ)りどころである法であります。また一般世間の法にも通ふところで、仏法の出世間(しゅっせけん)法なるに対し
世間法を意味せられるのであります(淳全 四八七)
と、広く世間法を含むことを教示されています。したがって、現在においては王法を、政治をふくむあらゆる社会生活の原理(国立戒壇論の誤りについて三九)と解釈するのは至極(しごく)当然です。
②「王臣」について
顕正会はあくまで日本の王は天皇であり、天皇の勅宣(ちょくせん)が広宣流布の必須条件であると主張しています。
しかし、現在の天皇は日本の象徴であり、一国の主権者は国民一人一人です。
この意味からして、
現代では、民衆が王であるとともに臣である(同五一)
と言われたのは当然のことです。
③ 「有徳王」について
これは教学部長時代の日顕上人が昭和四十一年の第二十九回学会本部総会の祝辞(大日蓮昭和四一年六月号一五)において、有徳王·覚徳比丘(びく)の例を挙げて、僧俗のあるべき姿を称賛する意味で引用されたものであって、『三大秘法抄』の意義を正式に解釈されたものではありません。池田大作に対して、日達上人および宗門をさらに外護(げご)するよう激励されたのです。
④「勅宣·御教書」について
勅宣や御教書は、為政者(いせいしゃ)が命令をしたり認可を与える際に発布(はっぷ)する令書です。『三大秘法抄』の「勅宣·御教書」にも、建設に対する為政者の許認可という意味合いが含まれています。
したがって、「勅宣·御教書」を、あえて「建築許可証」と解釈されたのです。
しかし、後に日顕上人は、
「勅宣·御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。
(近現代における戒壇問題の経緯と真義九八)
と仰せられています。
⑤ 「時を待つべきのみ」を「前以て建ててよい」などとねじ曲げた
昭和四十七年四月二十八日、日達上人は宗内全般に対して、
正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即(すなわ)ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。但(ただ)し、現時にあっては未(いま)だ
誇法の徒(と)多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇(しゅみだん)は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり
(達全二ー一三、昭和四七年六月号二)と「訓論」を発令されました。
これについて、当時の阿部教学部長(日顕上人)の『国立戒壇論の誤りについて』に、
従って正本堂は現在直ちに一期弘法抄、三大秘法抄に仰せの戒壇ではないが、将来その条件が整ったとき、本門寺の戒壇となる建物で、それを今建てるのであると、日達上人が明鑑(めいかん)あそばされ、示されたのが此の度の訓諭であろう(該書 六四)
と解釈しました。
これは、正本堂建立時は誇法の徒が多く、広宣流布の達成ではないものの、いよいよ折伏弘通に励み、近く広宣流布を達成して、名実ともに正本堂を御遺命の戒壇にするという、宗門僧俗の願望を、正本堂に込められたものです。
⑥ 「霊山浄土に似たらん最勝の地」を「大石寺境内」とごまかしている
大石寺が本門戒壇建立の地であることについては、日興上人の『富士一跡門徒存知事』に、
「駿河国(するがのくに)富士山は広博(こうぱく)の地なり。一には扶桑(ふそう)国なり、二には四神相応(しじんそうおう)の勝地なり」
(御書 一八七三)
とあり、本門戒壇は四神相応の地に建立すべきことを御教示されています。
第五十九世日亨上人は、四神相応を検討されて、
ここの地は、河合(かわい)よりやや朗開(ろうかい)せるも、半里をへだつる大石が原の景勝にしかず。ただちに富嶽(ふがく)を負い駿湾(すんわん)をのぞみ、一望千里臓宏(こうこう)たる高原にして、なお原始の処女林にあり。加うるに大道あり河沢(かたく)あり、四神相応の霊地なり(詳伝 二四一 )
と、大石寺が四神相応の霊地であると判じられ、大石寺こそが本門戒壇建立の地であることを御教示されています。
また、顕正会の前身である妙信講機関誌の『冨士』にも、
下条より約半里ほど離れた北方に大石ヵ原という若々(ぼうぼう)たる平原がある。後には富士を背負い、前には洋々たる駿河湾をのぞみ、誠に絶景の地であり、日興上人はこの地こそ、本門戒壇建立の地としての最適地と決められ、ここに一宇(う)の道場を建立されたのである。かくて、日興上人は弘安二年の戒壇の大御本尊をここに厳護されると共に、広宣流布の根本道場として地名に因(ちな)んで多宝富士大日蓮華山大石寺と号されたのである。これが日蓮正宗富士大石寺の始(はじま)りである
(富士 昭和三九年九月号二三)
との記述があります。
過去には妙信講も、大石寺こそ本門戒壇建立の地であると断じていたのであり、浅井の「霊山浄土に似たらん最勝の地を大石寺境内とごまかし」
という誹謗(ひぼう)は、自分たちの過去の言葉に言いがかりを付けているに過ぎません。

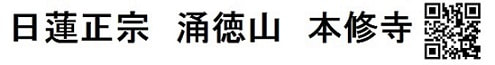
 RSSフィード
RSSフィード
